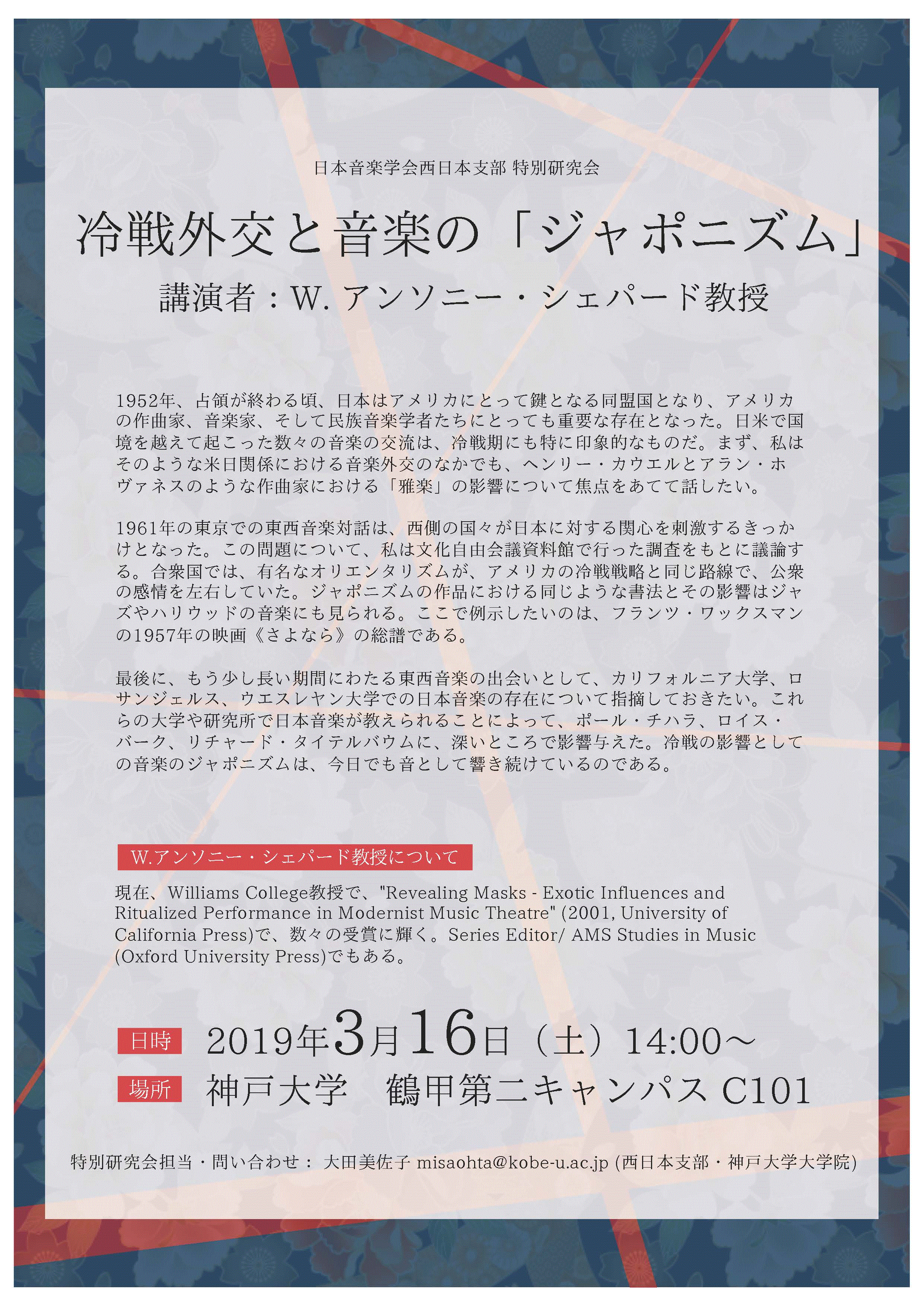アンソニー・シェパード教授講演会 「冷戦外交と音楽のジャポニズム」
- 日時
- 2019年3月16日(土)14:00~17:00
- 会場
- 鶴甲第2キャンパス [2] C101(当日案内表示があります)
- アクセス
- JR六甲道駅または阪急六甲駅より神戸市バス36番系統(鶴甲団地または鶴甲2丁目行),神大人間発達環境学研究科前下車
http://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/turukabuto-dai2.html [3] - 例会担当
- 大田美佐子(神戸大学)misaohta [at] kobe-u [dot] ac [dot] jp
- 主催/共催
- 日本音楽学会西日本支部, 神戸大学大学院人間発達環境学研究科 人間発達専攻 表現系講座
- 内容
- 講演
- 冷戦外交と音楽の「ジャポニズム」(概略的な通訳あり)
- W.アンソニー・シェパード
-
1952年,占領が終わる頃,日本はアメリカにとって鍵となる同盟国となり,アメリカの作曲家,音楽家,そして民族音楽学者たちにとっても重要な存在となった。日米で国境を越えて起こった数々の音楽の交流は,冷戦期にも特に印象的なものだ。まず,私はそのような米日関係における音楽外交のなかでも,ヘンリー・カウエルとアラン・ホヴァネスのような作曲家における「雅楽」の影響について焦点をあてて話したい。
1961年の東京での東西音楽対話は,西側の国々が日本に対する関心を刺激するきっかけとなった。この問題について,私は文化自由会議資料館で行った調査をもとに議論する。合衆国では,有名なオリエンタリズムが,アメリカの冷戦戦略と同じ路線で,公衆の感情を左右していた。ジャポニズムの作品における同じような書法とその影響はジャズやハリウッドの音楽にも見られる。ここで例示したいのは,フランツ・ワックスマンの1957年の映画《さよなら》の総譜である。
最後に,もう少し長い期間にわたる東西音楽の出会いとして,カリフォルニア大学,ロサンジェルス,ウェスレイアン大学での日本音楽の存在について指摘しておきたい。これらの大学や研究所で日本音楽が教えられることによって,ポール・チハラ,ロイス・バーク,リチャード・タイテルバウムに,深いところで影響与えた。冷戦の影響としての音楽のジャポニズムは,今日でも音として響き続けているのである。
- 講演者 W. Anthony Sheppard教授について
- 現在,Williams College教授で,"Revealing Masks - Exotic Influences and Ritualized Performance in Modernist Music Theatre" (2001, University of California Press)で,数々の受賞に輝く。Series Editor/ AMS Studies in Music (Oxford University Press)でもある。